| 1.はじめに
企業年金加入者の受給権保護を強化した確定給付企業年金法が平成13年6月8日に成立し,平成14年4月から施行された。
また,継続審議となっていた本人の運用次第で年金給付額が変わる確定拠出年金法も平成13年6月22日に成立し,この方は先行して平成13年10月から施行された。
こうして,21世紀初頭のわが国企業年金制度の大枠を決める法律が出揃った。
2.確定給付企業年金の概要
確定給付企業年金は,あらかじめ将来の年金受給額を決めておく企業年金規約を前提として導入する企業年金制度で,内部が「規約型」と「基金型」の2制度に分かれており,従来からある確定給付型企業年金制度の持つ問題点の改善を図り,既存の制度を導入している企業に適応できるよう再設計した制度で,受給権保護の規定を入れたことのほか,特に各年金制度間の移行について積極的な規定が設けられている点に特徴があり,種々の制度を組み合せて導入することが可能な仕組みになっている。
次に確定拠出年金は,いわゆる「日本版401(k)」として,新規に導入された企業年金制度である。この制度のポイントは,企業もしくはその従業員が掛金を拠出し,それをレコードキーピングする外部の運営管理機関が従業員ごとに「持分」として区分勘定を持ち,常時各人の「年金資産高」を明確にすることで各人の自己責任で運用させるもので,原則として60歳に達した以降に,これを原資として年金や一時金を支給する制度である。
そして,この制度にも税制上の特典を与え,老後の年金生活の安定を図る上で「確定給付型」制度の対極にある制度として,今後期待されているものである。
以下においては,このうち確定給付企業年金制度について述べる。この制度の新設により,既存の法人税法上の制度として規定されていた適格退職年金制度はこれを収束し,主として「規約型」企業年金に取り込むことで受給権保護の観点を進めて年金財源の管理や資産運用を厳格化できる。また,厚生年金基金については,「代行部分」の国への返上を認めることとした場合,代行返上後の基金の主な受け皿として「基金型」企業年金が用意されたことで,希望する企業には公的年金の一部代行という重圧を回避する道を開いたことになる。そして,既存の適格退職年金は,このような形で収束するとしても,契約数が大量であることもあり,また,移行に当たっては労使間の協議を整えるなど時間を要することもあるので平成24年3月31日までの10年間の収束期間が与えられることとなった。
法案の提出理由の厚生労働省説明から新制度創設の趣旨が分かるので,ここでその冒頭の部分を引用してみると,以下のとおりである。
「わが国は,少子高齢化の進展,産業構造の変化等社会情勢が大きく変化しており,公的年金に上乗せして給付を行う年金制度についてもこれらの変化に対応することが要請される。今回の法案では,確定給付型の企業年金について受給権保護等を図る観点から,労使の自主性を尊重しつつ統一的な枠組みのもとに制度の整備を行うもので,これにより公的年金の土台としつつ,確定拠出年金と相まって国民の自主的な努力を支援する仕組みを整備するものである。」
そして,主な内容として次の5点を挙げていた。(以下は概要を省述したもの)
<1> 確定給付企業年金の基本的な仕組み
<2> 給付は次の4種類
i 老齢になった場合→老齢給付金
ii 脱退した場合→脱退一時金
iii 障害を負った場合→障害給付金
iv 死亡した場合→遺族給付金
<3> 受給権保護の規定
<4> 年金制度間の移行
<5> 税制上の措置
以上であるが,これを適格退職年金と比較した場合,企業年金の基本スキームは,年金規約に基づく制度設計,掛金計算,制度受託会社等は同一の流れにあるが,(イ)老齢給付金等年金支給をするものについては必ずしも終身年金とすることを要件とせず,有期年金を認めることとしたこと,(ロ)給付の種類に障害給付が加えられたこと(強制ではない),(ハ)制度の受給権保護を図る観点から種々の守るべき規定が新設されたこと,(ニ)年金制度間移行を積極的に認めたこと,などは新規に付加された点である。
また,制度間移行に関連しているが,従来からある適格退職年金制度の将来に向かっての収束を打ち出した。
ここで,確定給付企業年金の「規約型」と「基金型」のスキームについて述べるが,これは図示したほうが分かりやすいので(図表1)を掲げておくことにする。
| 図表1 規約型と基金型のスキーム図 |
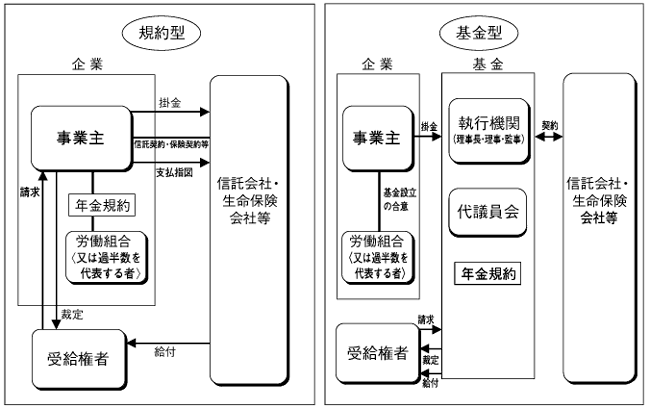 |
確定給付企業年金の特徴となっている「受給権保護」「代行返上」「制度間移行」の3点について,少し解説を加えておこう。
3.受給権保護の措置
制度加入者の将来の年金等受給権を確実なものとしてゆくためには,年金制度の維持管理に関して企業をはじめ関係者の努力が必要となることはいうまでもないことだが,このための措置を具体的に以下に述べる3つの側面から規定している。
<1> 積立義務
最初に,積立義務の内容を分かりやすくするために新法の流れをフォローすると,
(i)事業主に給付支給の財源となる年金資産の積み立てを義務付ける。
(ii)積立の長期的維持実現のために,少なくとも5年に1度,料率等の再計算の実施を義務付ける。
(iii)毎年の制度決算時,財政検証を義務付ける。内容は,年金財政が長期計画通り進んでいるかの検証(=継続基準という)と,過去期間の既発生給付に見合う資産の確保状況の検証(=非継続基準という)を行う。
(iv)検証の結果,積立額が上記の非継続基準による額を下回って積立不足がある場合は,一定期間内に解消するように,企業にその分の掛金を追加拠出することを求める。
という仕組みになっている。
<2> 受託者責任
このように,加入者の受給権の保護を図ることに制度の重点が置かれたが,この立場を補強する意味で,企業や受託機関等企業年金の運営管理に関わる者に対して加入者等に対する「忠実義務」などの責任について規定するとともに,「利益相反行為の禁止」などの「行為準則」を明確化した。従来,事業主(基金の理事)の行為準則については,厚生年金基金には一応の規定があったが,運用機関の行為準則についての規定はなかった。
<3> 情報開示
これは,直接には「業務状況の周知」として規定されている。加入者に周知させるべき事項としては,年金規約の内容,掛金の納付状況・資産の運用状況・制度の財政状況等の年金財政決算に関する情報開示報告が中心となる。これらの情報開示が必須となれば,加入員の年金制度への関心が高まり,企業や受託サイドにおいてもいわゆる手抜きや内容の糊塗などができなくなり,問題の発生に対する対処も俊敏になるというものである。
この規定も,厚生年金基金には不完全ながら従来からあったが,適格退職年金にはまったくなかったものである。また,衆議院において確定給付企業年金法案が可決されるに当たって,この情報開示については事業主等に対し実情を踏まえた適切な指導を行うこととする付帯決議が行われた。
4.代行返上
制度間移行が大胆に認められるようになったと述べたが,このような流れの中で厚生年金基金を他の企業年金制度に移行する場合には(図表2)に示すように厚生年金基金の給付のうち,本来の企業給付でないため他の企業年金制度に移行することができない「代行給付」部分については国の厚生年金保険へ戻し入れることを認めることとした。これを一般に「代行返上」という。
図表2 厚生年金基金を他の企業年金制度に移行する場合
厚生年金基金が確定給付企業年金に移行する際,これまでの代行給付の支給の義務を国に移転する |
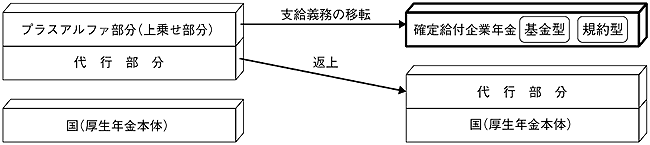 |
つまり,代行返上とは,結果として厚生年金基金制度を消滅させることであり,厚生年金基金の「解散」に似た行為である。(図表2)で示すプラスアルファ部分(上乗せ部分)が基金型企業年金に引き継がれるという意味で解散の場合とは異なるが,消滅する点では同一である。
平成12年4月から開始した事業年度から,企業は退職給付会計を導入することになったわけだが,この結果,「代行給付」部分が企業の退職給付債務(P.B.O)を予想外に膨張させる要因になるという認識が企業間に一般化した。本来は国の支給債務である公的年金を企業の支給債務として肩代わりする形の部分であるだけに,企業に余計な負担を強いるものとして認識されることになったのである。
主として,運用難と会計基準という2つの重苦しい負担から,少なくとも「代行部分」については,解放されたいという企業要望が,種々の経緯を経て厚生労働省を動かすところとなり,確定給付企業年金法の立法を機に「代行返上」の道を開かせたといわれている。これは適格退職年金制度の売り止めと収束のために,同様に受け皿制度として確定給付企業年金制度を活用することを認めたことと軌を一にするものといえる。
さて,代行返上は将来分のみということを認めていない。したがって,返上する場合は,過去にさかのぼってすべて返上するということになる。しかし,このため直ちに返上できないという問題がある。受け入れ側の社会保険庁の準備が必要になるからである。
厚生年金基金は,通常2つの段階を経て確定給付企業年金に移行することになる。まず第1に,将来期間分の代行部分の停止(いわゆる将来返上)の認可を受け,第2に過去期間分の代行部分の返上(いわゆる過去返上)の認可等を受けることになる。
将来返上については,事業主・加入員および労働組合の同意,受給者等への説明の手続きを経たうえで代議員会の4分の3以上の同意を得て,厚生労働省へ認可申請をする。平成14年4月1日から認可が開始され,平成16年6月1日現在で790基金が認可を受けている。
また,将来返上の認可を受けた厚生年金基金は,過去返上の認可申請までに加入員および中途脱退者等の記録整理を仮完了している必要がある。記録整理は,<1>加入員番号の整理,<2>加入員記録と中途脱退者記録との整理,<3>加入員記録と厚生年金保険の被保険者記録との整理の3つの作業を行う。過去返上については,確定給付企業年金法第111条または第112条に基づき,平成15年9月1日から認可が開始され,平成16年6月1日現在で390基金が認可を受けた。
過去返上の認可等を受けた厚生年金基金は,認可日に解散(みなし)または消滅し,確定拠出企業年金法に基づく規約型企業年金または基金型企業年金のいずれかの形で運営を行っていくことになる。
過去返上の認可申請時には,規約型企業年金に移行する基金は,確定給付企業年金の規約の承認申請を同時に行う。基金型企業年金に移行する基金は,確定給付企業年金の規約の添付が必要になる。
このため,過去返上の認可申請の約6か月前までには,受託機関に給付設計や掛金計算等の数理計算を依頼し,移行する確定給付企業年金の制度内容を確定し,規約を作成することになる。また,認可申請までに,受給者等に対し,<1>代行返上のしくみと移行後の確定給付企業年金の内容,<2>社会保険庁から代行部分が支給されること,<3>至急遅延の可能性があること,<4>代行部分の支払口座,<5>代行返上に係わる問い合わせは基金に行うこと,等の周知を行うことも必要とされる。
厚生年金基金連合会(平成17年10月から企業年金連合会)のまとめている平成17年6月1日現在の状況は次のとおり。
◎厚生年金基金
1.基金数
| |
| 合 計 |
単独設立・連合設立 |
総 合 設 立 |
773
(697) |
234
(160) |
539
(537) |
|
| |
(注) カッコ内は,将来返上を除く。
|
2.代行返上基金
| |
| 将来返上 |
現存基金
(厚生年金基金) |
過去返上
(確定給付企業年金数) |
解 散 |
| 822 |
76 |
699 |
48 |
|
| |
(注) 将来返上から過去返上の間に合併した基金が2基金ある。
|
3.解散基金
| |
| 解 散 計 |
平成17年4月〜6月 |
平成16年度 |
平成15年度 |
| 415 |
7 |
81 |
92 |
|
◎確定給付企業年金
| |
| 合 計 |
基 金 型 |
規 約 型 |
1,180
(691) |
557
(549) |
623
(142) |
|
| |
(注) カッコ内は,厚生年金基金からの移行。
|
法文上,代行返上の認可日以後は,厚生年金基金では厚生年金の代行はしないことになる。したがって,認可日以後,免除保険料としての扱いはなくなり,社会保険料(厚生年金保険料)は全額国へ納付することとなる。
なお,この過去分の年金原資の返還は,国債や上場有価証券など一定基準にあてはまる,いわゆる「現物」による返還が認められることになっている。
5.制度間移行の措置
確定給付企業年金法の特徴の一つは,既存の年金制度も含めて各年金制度間で「制度移行」を認めた点にある。それは単にやむを得ざることとして消極的に認めるというものではなく,ある意味で移行を前提にして法の制定が行われたといえるほど積極的なものである。
ここでは,認められる移行のパターンを分類してその特徴を述べることにする。
(1) 確定給付企業年金制度の中での移行
これは「規約型」と「基金型」との間での移行で,相互に移行できる。
(2) 確定給付企業年金と厚生年金基金との間での移行
この場合も相互に移行できるが,このうち厚生年金基金から確定給付企業年金に移行するケースが「代行返上」の起きる場合である。この移行をするには基金の代議員会において代議員定数の4分の3以上の多数により決議して,厚生労働大臣の認可を受けることが必要である。
(3) 確定給付企業年金から確定拠出年金への移行
この場合は,給付型から拠出型への一方通行の移行しか認められていない。これは,確定拠出型はその資産が加入者の個別管理というまったく別の方式に変わるからであるが,観点を変えてみると企業会計上の負債計上の問題と関連する。すなわち,この移行をすれば,企業の会計上の退職給付債務の計上額をその分縮小することができるのである。
以上の移行パターンをまとめて図示すると(図表3)のようになる。
| 図表3 制度間移行の措置 |
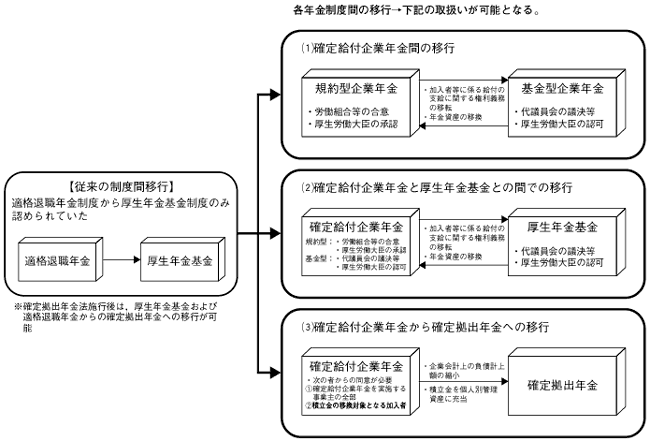 |
平成16年6月に成立した年金制度改革法により,確定給付企業年金関係では,ポータビリティの拡充が盛り込まれた。
現在,確定給付企業年金の設立事業所間で加入者が転職する際,権利義務の移転承継について双方の年金規約で定めている場合は,転職先の確定給付企業年金に個人の年金資産(脱退一時金相当額)を移換することが可能となっている。
ただし,厚生年金基金の設立事業所から他の厚生年金基金の設立事業所に転職した場合及び確定給付企業年金の設立事業所に転職した場合は,年金資産の移換はできず,脱退一時金を受けることになる。また,厚生年金基金及び確定給付企業年金から,確定拠出年金への資産移換も認められていない。
改正により,平成17年10月からはこれらの企業年金間の資産移換が可能となる(確定拠出年金から企業年金への移転は不可)。転職の際,加入者の申し出によって資産移換が可能となるが,加入者が申し出なかったり,転職先の企業が引き受けない場合は,企業年金連合会(平成17年10月から厚生年金基金連合会を改称)に資産が移換され年金給付を通算する。
また,厚生年金基金の設立事業所から確定給付企業年金の設立事業所及び確定拠出年金の設立事業所への転職の場合,代行部分相当額は企業年金連合会から支給される。
確定給付企業年金の中途脱退者や解散企業年金の加入者の年金資産は,企業年金連合会に移換され年金として支給される。
6.適格退職年金の移行
それでは,制度間移行の最後に適格退職年金の移行について述べておくこととする。
この制度は,平成14年4月以降10年以内に収束しなければならないので,いずれにしても他の年金制度に移行することになる。そうしなければ10年後には消滅の運命にあるわけである。
この制度の移行先として適当な制度は,やはり,規約型の確定給付企業年金であろう。なぜなら,この制度が一番内容の類似した制度だからである。また適格退職年金には,規模の小さい企業が多くある。このことを考慮するとなるべく簡便な制度へ移行することを望む企業も多くあると考えられ,この受け皿制度として既存の「中小企業退職金共済制度」(中退共)が対象とされた。この制度は,将来の給付額の計算は掛金月数によって決まる方式のため,移換金額を被共済者に係る掛金納付月数に換算して通算することにしている。
適格退職年金から中退共への資産の移換は,次のような手順により行われる(法施行後10年間限りの経過措置)。
<1> 労使間で適格退職年金の資産を1人ごとの持ち分に分割する。
(仮に,積立不足があっても合意があれば,その時点で保有する資産のみを分割することも可能)
<2> 中退共への月額掛金を決める。
通常,中退共に新たに加入する際,掛金の2分の1(上限5,000円)を加入後4か月目からの1年間,国が助成しているが,適格退職年金から移行する場合の助成はない。
<3> 適格退職年金制度の資産のうち事業主拠出分に相当する額の範囲内で,中退共に加入する時に決めた月額掛金の120か月分に見合う額を上限として「勤労者退職金共済機構」に引き渡すことができる。
引渡金額(適格退職年金資産のうち事業主拠出分に相当する額の範囲内)
=確定給付企業年金法付則別表から定まる金額×(被共済者ごとに決めた月額掛金÷1,000円)
<4> このとき引き渡した金額に応じて決められる月数については,移行後の掛金納付月数と通算することができる。ただし,適格退職年金の加入者であった期間の月数(120か月を超えるときは120か月)を限度とする。
<5> 1人ごとの持分が引渡金額を超える場合は,その額を従業員に返還する。
以上,新制度下における制度移行について述べてきたが,これらをまとめて表示すると(図表4)のようになる。
| 図表4 新しい企業年金制度の体系 |
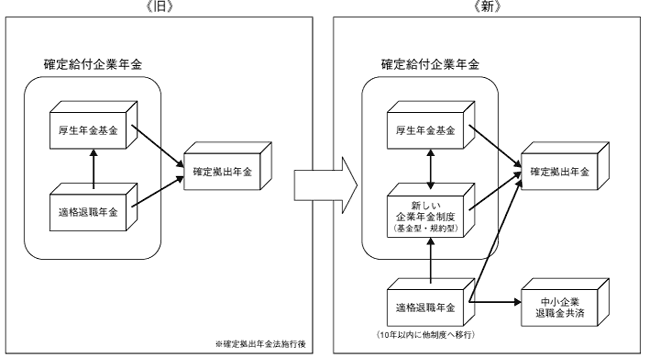 |
7.企業の視点からの新制度の評価
ここまでは,確定給付企業年金法を中心に,わが国21世紀初頭の企業年金制度のあり方を決定付ける各制度の内容および相互関連について述べた。
次に,観点を変え,これらの制度を活用する企業の立場から,あるいは企業が採用する制度如何が自分の老後生活に大きく影響する従業員の立場から,どのように評価されるかについて私見を述べて締めくくりとしたい。
規約型は適格退職年金制度と類似した制度であることは明白である。新制度では,年金財政チェック等の規制強化の面はあるが,税務取扱い上,両者はほとんど変わりはない。また,基金型は代行部分を返上した厚生年金基金であるともいえ,もともとその目的で制度化されたものであるが,現実に厚生年金基金からこの制度に移行すれば税制面では多少後退する形となる。
新制度は,基本姿勢として,加入資格,給付内容などは労使合意による年金規定で独自に決められることになっており,例えば,給付については年金でなく一時金で支給できるし,終身年金が原則である厚生年金基金とは異なり,年金も全額有期年金で支給することができるなど弾力的なところがあるが,企業サイドからみて現行制度より明らかに優れていると指摘できるほど差別化されたところは見当たらないように思える。
結論として,企業にとり,従来より特段有利な制度ができるわけではないとするのが率直な評価であろう。
8.新しい企業年金の動向
そこで,企業は,新制度のどこにメリットを求めることができるかという質問が起こるわけであるが,その回答は「これら各制度の組み合わせ導入」の中にあるのではないかと考えている。
その第一は,組み合わせにより「代行返上」ができるという点である。今まではしたくても「できなかった」のであり,どうしてもという場合は,基金の解散しかなかったのであるから,厚生年金基金を重荷と思っている企業にとっては大変な朗報といえよう。
その第二は,「各制度の組み合わせ」そのものの中に効率化を模索していこうとする立場をとる企業の場合である。従来はできなかったいろいろな制度の組み合わせができることとなった。組み合わせを工夫すれば企業にとっても従業員にとってもメリットのある方式が構築できる余地が生まれたといえるのではないだろうか。それは単に各制度の利用割合を組み合わせる方法,例えば,規約型企業年金に全体の3分の2を移行し,残りの3分の1は確定拠出年金に移行するといった組み合わせである(これを「制度組み合わせ型」と呼ぶことにする)。
もう一つは,一般に「ハイブリット型」といわれるもので,例えば,一つの制度の中に確定給付型の要素と確定拠出型の要素を併せ持つ新しい自社向けの年金制度を設計する方法である(これを「ハイブリット型」と呼ぶことにする)。この設計は,必ずしも容易ではないが,すでにアメリカなど先進国にその事例を見ることができ,例えば,「キャッシュバランスプラン(CBプラン)」といわれているアメリカの制度などはその典型的な制度であり,わが国の企業間でも早くから関心の高い制度の一つとなっている。
このように,確定給付企業年金法および確定拠出年金法が施行されたことを受けて,わが国の今後の企業年金制度は新法の内容を生かす形で,いわゆる「組み合わせ型」を中心に各企業が創意工夫を重ねて新しい方向に広く踏み出すことになったわけである。
|